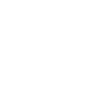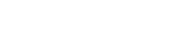本文
個人町民税・県民税について
個人町民税・県民税について
個人町民税・県民税は、1月1日現在に富士見町に住んでいる方に、前年1月1日から12月31日までの1年間の所得に応じてご負担をお願いするものです。
個人町民税と個人県民税を合わせて、一般に「個人住民税」といいます。なお個人県民税の申告と納付は、個人町民税と合わせて行います。(以下「町県民税」として説明します。)
1月2日以降、富士見町に在住しなくなった場合(他市区町村へ転出された場合や死亡された場合)でも本年度の町県民税については、富士見町へ納めていただくことになります。
税率について
町県民税は、所得割と均等割に区分されます。
<町県民税の税率>(分離所得の税率は異なります)
|
|
町民税 |
県民税 |
|
所得割(標準税率) |
6% |
4% |
|
均等割 |
3,500円 |
※2,000円 |
※ 個人県民税には、平成20年度から令和9年度まで、「長野県森林づくり県民税<外部リンク>」として500円が上乗せされています。詳しくは長野県のホームページをご確認ください。
- 所得割:前年1年間の所得金額を基礎として算出いたします。
- 均等割:町民税は3,500円(標準税率)、県民税は2,000円です。平成26年度から令和5年度までの10年間に限り「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の制定により、個人町民税500円、県民税500円の合計1,000円が加算されます。
- 所得割と均等割の合計が、町県民税の年税額となります。
令和6年度以降の個人町民税・県民税均等割及び森林環境税について
個人町民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円が引き上げられ賦課徴収されておりましたが、この臨時的措置が令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
| 令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
| 国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
| 県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
| 町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
| 計 | 5,500円 | 5,500円 | |
所得割について
課税の対象者
総所得金額が次の計算で算出される金額を超える方
35万円 × (扶養親族の人数 + 1) + 10万円 + 32万円 (32万円は扶養親族がいる場合のみ加算)
(扶養親族がいない場合は、総所得金額が45万円を超えると課税となります。)
所得割の税額計算
- 総所得金額 - 所得控除合計額 = 課税標準額
- 課税標準額 × 税率(6%+4%) = 税額控除前所得割額
- 税額控除前所得割額 - 税額控除額(※) = 所得割額
※調整控除、配当控除、住宅ローン控除、寄付金控除などがあります。
均等割について
課税の対象者
合計所得金額が次の計算で算出される金額を超える方
28万円 × (扶養親族の人数 + 1) + 10万円 + 16万8千円 (16万8千円は扶養親族がいる場合のみ加算)
(扶養親族がいない場合は、合計所得金額が38万円を超えると課税となります。)
所得控除について
納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
雑損控除
(1)、(2)のいずれか多い金額
(1)(損失額-保険金・損害賠償金)-所得金額×10%
(2)災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
次のいずれか一方のみ適用となります。
医療費控除 (最高200万円)
(前年に支払った医療費) - (保険金等で補てんされる金額) - (所得金額の5%または10万円のいずれか少ない金額)
セルフメディケーション税制 (最高88,000円)
(前年中に支払った特定一般医薬品等購入費) - (保険金などで補てんされる金額) - (12,000円)
社会保険料控除
前年中に支払った、国民健康保険料、国民年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの社会保険料の支払金額が対象となります。
小規模共済掛金
前年中に支払った掛け金の全額が対象となります。
生命保険料控除
前年中に支払った一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料などの社会保険料の支払額
| 支払保険料額 | 控除額 | ||
| (1)平成24年1月1日以降契約 (新契約) |
12,000円以下 | 支払保険料の全額 | 合計額の適用限度 70,000円 |
| 12,001~32,000円 | 支払保険料の 1/2 + 6,000円 | ||
| 32,001~56,000円 | 支払保険料の 1/4 + 14,000円 | ||
| 56,001円以上 | 28,000円 | ||
| (2)平成23年12月31日以前契約 (旧契約) |
15,000円以下 | 支払保険料の全額 | |
| 15,001~40,000円 | 支払保険料の 1/2 + 7,500円 | ||
| 40,001~70,000円 | 支払保険料の 1/4 + 17,500円 | ||
| 70,001円以上 | 35,000円 | ||
| (3)(1)と(2)の両方 | (1) + (2)(適用限度28,000円) | ||
地震保険料控除
短期損害保険料および、平成19年以降に締結された長期損害保険料は控除対象になりません。
| 支払保険料 | 計算式 | 限度額 | |
| 地震保険 | 1円以上 | 支払った地震保険料の 1/2 | 最高25,000円 |
| 旧長期損害保険 | 5,000円以下 | 支払保険料の全額 | |
| 5,000~15,000円 | (支払った保険料の金額の合計の額)× 1 /2 + 2,500円 | 最高10,000円 | |
| 15,000円以上 | 一律10,000円 | ||
| 支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方(別契約)の場合 合計 最高25,000円 | |||
障害者控除
納税者本人、配偶者、扶養親族が以下の表に当てはまる場合に対象となります。
| 障害者控除 | 特別障害者控除 | |
| 身体障害者手帳 | 3級以下 | 1級、2級 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 2級、3級 | 1級 |
| 療育手帳 | B | A |
| その他 | 65歳以上で、障害者に準ずるものとして町長や福祉事務所長の認定を受けている方 | 65歳以上で、特別障害者に準ずるものとして町長や福祉事務所長の認定を受けている方 |
| 控除額 | 26万円 | 30万円 |
特別障害者控除になる方と同居を常にされている場合 : 控除金額 53万円
※障害者控除対象者認定証の発行を希望される方は介護高齢者係(役場1階3番窓口)へ申請してください。
寡婦控除・ひとり親控除
以下の表に当てはまる場合に対象となります。また、死別の場合、生死が明らかでない場合も含まれます。
| 寡婦控除 | ひとり親控除 | ||
| 死別 | 離婚 | 死別、離婚、未婚 | |
|
合計所得金額が500万円以下 |
合計所得金額が500万円以下で、総所得金額が48万円以下の扶養親族(ほかの方の扶養になっていない)がいる |
合計所得金額が500万円以下で、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子(ほかの方の扶養になっていない)がいる |
|
| 控除額 26万円 | 控除金額 30万円 | ||
勤労学生控除
合計所得金額が75万円以下で、特定の学校に在学されている方
控除金額 26万円
扶養控除
合計所得金額が48万円以下で、扶養している親族が対象となります。
| 19歳以上23歳未満である場合 | 控除金額 45万円 |
| 70歳以上である場合 | 控除金額 38万円 |
| 70歳以上で同居している場合 | 控除金額 45万円 |
| その他の控除対象扶養親族 | 控除金額 33万円 |
※16歳未満の年少扶養対象者については、控除金額はありませんが、所得に応じて町県民税額に影響がある場合があります。
配偶者控除
| 町県民税控除額 | |||
| 本人の合計所得金額 | |||
| 控除区分 | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
| 控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
| 町県民税控除額 | |||
| 本人の合計所得金額 | |||
| 配偶者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 |
| 48万円超 95万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
基礎控除
| 合計所得 | 町県民税控除額 |
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |
税額控除について
調整控除
所得税から住民税への税源移譲に伴う調整措置の一環として、平成19年度分以降の町県民税において、所得税と町県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するため調整控除が設けられました。他の税額控除に先立ち、所得割額から控除されます。
| 合計課税所得金額 | 計算方法 |
| 200万円以下 | 次の(1)と(2)のいずれか小さい金額の5% |
| (1)人的控除額の差の合計額 | |
| (2)合計課税所得金額 | |
| 200万円超 | 〔所得税との人的控除額の差の合計-(合計課税所得金額-200万円)〕×5% ※上記計算結果が2,500円未満の場合、2,500円(町民税1,500円・県民税1,000円) |
配当控除
株式の配当などの配当所得があるとき(申告不要及び上場株式等で申告分離課税を選択したものを除く。)は、その金額に下表の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
| 課税所得金額等 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超える場合 | ||||
| 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||
| 町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | |
| 利益の配当、余剰金の分配、金銭の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く。) | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 証券投資信託の利益の分配(一般外貨建当証券投資信託の収益の分配を除く。) | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 一般外貨建等証券投資信託の利益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
外国税額控除
その年において外国所得税を納付することとなる場合、その年分の所得税と復興特別所得税の合計額(住民税の場合は、町民税及び県民税の所得割額)から控除限度額を限度として外国所得税額を控除します。控除は、所得税及び復興特別所得税から控除し、控除しきれない場合に県民税(所得割額)、町民税(所得割額)から順次控除します。
詳しくは、国税庁ホームページ 「外国税額控除」<外部リンク> をご確認ください。
住宅借入金等特別控除
平成22年度分から令和20年度分までの町県民税(所得割)の納税義務者が、次の(1)及び(2)の要件を満たす場合には、所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除と前年分の所得税の課税所得金額等の合計額に5%を乗じた金額(9.75万円を限度とする。※1)とのいずれか小さい金額が町県民税額から控除されます。
(1)平成21年から令和7年までの間に居住の用に供して住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合において、所得税額(※2)から控除しきれない住宅借入金控除等特別控除額(※3)があること
(2)控除を受けようとする年度分の町県民税の申告書または前年分の所得税の確定申告書に住宅借入金等特別控除額の控除に関する事項の記載があること。
※1 平成26年4月から令和3年までの間に居住の用に供し、かつ、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合は、課税総所得金額等の合計額に7%を乗じた金額(13.65万円を限度)となります。
※2 住宅借入金等特別控除額、政党等寄付金特別控除額、認定NPO法人等寄付金特別控除額、公益社団法人等寄付金控除額、住宅耐震改修特別控除額、住宅特定改修特別控除額、認定新築住宅等特別控除額、災害免除額、外国税額控除額がないものとして計算した所得税額です。
※3 特定増改築等借入金等特別控除を適用しないで計算した額です。
手続きについて
所得税について住宅借入金等特別控除の申告書を提出すればよく(初回は必ず確定申告が必要です。)、また、2回目以降は年末調整の際、給与支払報告書等に住宅借入金等特別控除可能額等一定の事項の記入がされていることで対応されますので、特に町県民税に関する申告の必要はありません。
詳しくは、国税庁ホームページ 「住宅借入金等特別控除」<外部リンク> をご確認ください。
町県民税が非課税の方(所得割、均等割)
- 賦課期日(1月1日)現在、生活保護を受けている方
- 合計所得金額が135万円を超えていない未成年者または障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除を受けている方
町県民税の減免
災害にあった、生活保護を受給するようになったなど生活が著しく困難になり納税が難しくなった方は、町県民税が減免される場合があります。減免を希望される方は、納期限の7日前までに財務課へ減免申請書を提出してください。
家屋敷について
家屋敷課税について
1月1日現在において、富士見町に住所がなく、富士見町内に別荘や別宅、事務所などを所有されている個人の方などには、町県民税(家屋敷)として均等割のご負担をお願いしております。
この家屋敷課税は、固定資産税とは異なり、富士見町から受ける行政サービス(消防、防災、衛生、道路など)に対して、一定の負担をお願いしているものです。
家屋敷の該当とならない場合
- 居住地において個人住民税が非課税である
- 貸付目的の住宅や他人に1月1日現在貸している住宅であり、所有者本人が自由に居住することができない
- 老朽化が激しく直ぐに居住することができない、または居住するには修理が必要とする住宅である(電気、ガス、水道設備が欠けている状態など)
- 単なる個人の資材置き場や倉庫などで、居住用の建物ではない など
上記に該当する方は、毎年6月に送付している納税通知書に同封しております「申告はがき」を使用し、6月中に申告してください。