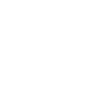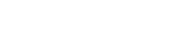本文
国保の給付
療養の給付
医療機関の窓口で資格確認書等を提示すれば、下記のような医療にかかった費用の一部(一部負担金)を支払うだけで済みます。残りの費用は国保が負担します。
(療養の給付)
- 診察
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院及び看護
- 在宅療養及び看護
- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)
|
0歳〜6歳(小学校就学前) |
2割 |
| 小学校就学後〜69歳 |
3割 |
|
70歳〜74歳 |
【一般】 2割 |
|
【※現役並み所得者】 3割 |
※現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも下記のいずれかの場合は、「一般」の区分と同様となります。
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、収入が383万円未満
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で、収入合計が520万円未満
- 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含めた収入合計が520万円未満
療養費について(あとから費用が支給される場合)
下記のような場合は、いったん医療機関で全額自己負担していただき、あとから国保に申請して認められると、自己負担分を除いた分について、療養費が支給されます。
- やむをえない理由で、資格確認書等を持たずに医療機関にかかったときや、海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
- 輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代
※医師が必要と認めた場合にのみ適用されます。 - 針・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
※医師が必要と認めた場合にのみ適用されます。 - 骨折やねんざなどで、保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
| 1. | 国民健康保険資格確認書等 |
| 2. | 領収書 |
| 3. | 医師の診断書・診療報酬明細書等 |
| 4. | 世帯主名義の振込口座のわかるもの(預金通帳など) |
| 5. | 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) |
高額療養費について
同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として支給します。 自己負担限度額は70歳未満の方と70歳以上の方(後期高齢者医療保険の方は除く)では異なります。また、同じ世帯で高額の自己負担額(70歳未満については21,000円以上のもの)が 複数あった場合には合算することができます。
高額療養費の支給に該当する世帯には、原則として診療月の2ヵ月後に通知しますので、内容をご確認のうえ申請してください。
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額)(3回目まで) |
4回目以降※1 |
|
ア (所得901万円超) |
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
|---|---|---|
|
イ (所得600万円超~901万円以下) |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
ウ (所得210万円超~600万円以下) |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
|
エ (所得210万円以下) |
57,600円 |
44,400円 |
|
オ 住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 過去12か月間で、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合、限度額が引き下げられ、「4回目以降」の限度額を超えた分が支給されます。
|
所得区分 |
自己負担限度額(月額) | ||
| 3回目まで | 4回目以降※1 | ||
|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |
|---|---|---|---|
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
| 3回目まで | 4回目以降※1 | ||
|
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円※2 | 57,600円 | 44,400円 |
|
低所得者2 (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 24,600円 | |
|
低所得者1 (住民税非課税世帯) |
8,000円 | 15,000円 | |
※1 過去12か月間で、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合、限度額が引き下げられ、「4回目以降」の限度額を超えた分が支給されます。
※2 年間(8月〜翌年7月)の限度額は144,000円です。
窓口での支払いを限度額までにできます
外来でも、入院でも、窓口での支払いから高額療養費対象分を除き、各々の自己負担限度額までにできる「限度額適用認定証」が交付できます。(個人単位・一医療機関単位)
70歳以上75歳未満の方は、現役並み所得者及び住民税非課税世帯の方のみ交付となります。
認定証が必要なときは国保へ申請してください。
ただし、保険料を滞納していると交付できないことがあります。
入院時食事療養費について
入院中の1食の食事にかかる費用のうち510円を被保険者負担とし、残りの食事費用を国保が負担します。住民税非課税世帯の被保険者は、さらに負担が減額されますので、入院の際は国保へ申請してください。
※入院時の食事代は高額療養費の支給対象になりません。